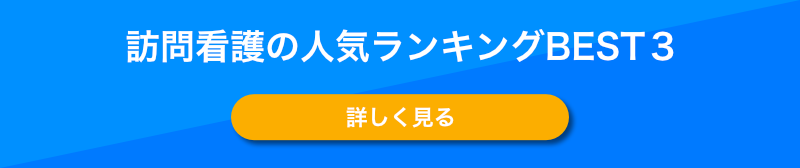本記事は一部のサービスのリンク先にプロモーションを含みます。
少子高齢化が進むなか、介護の必要性は年々増している一方で、経営が悪化して倒産してしまう介護事業所は多くあります。介護事業所は介護保険制度のもと成り立っており、よりよい経営状況を作るためには介護報酬の仕組みをしっかりと理解し、利益を伸ばすことが重要です。

ここでは、介護保険制度を分かりやすく説明した上で、介護保険ビジネスの仕組みについて紹介します。このページを読むことで、介護保険制度や介護報酬の仕組み、それによる介護のビジネスモデルや将来性について理解できます。
- 介護で起業を考えているが、儲かるか不安
- 現場の仕事は理解しているが、介護保険や介護報酬の仕組みは分からない
もくじ
介護保険ビジネスの仕組み(ビジネスモデル)
介護保険とは、介護認定を受けている(介護を必要とする)人や、その家族に対して、国や地方自治体が介護費用の一部を負担する社会保障制度のことです。
①介護保険制度は加入者(被保険者)と、②サービス提供事業者と、③市区町村(保険者)の3者の間で成り立っています。サービス提供事業者が被保険者に実施した介護サービスに対する対価のことを介護報酬といい、3年に1度の法改正で見直されます。
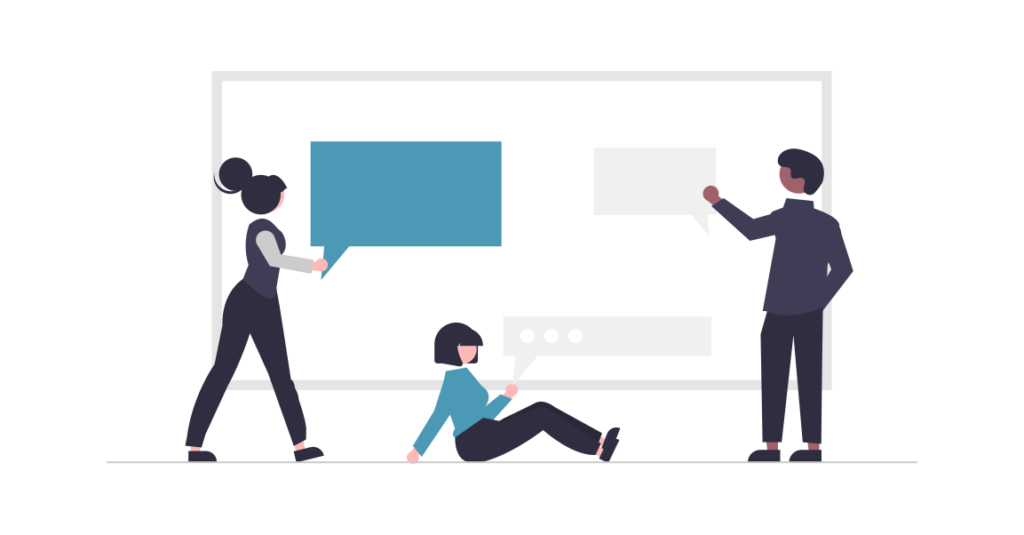
介護報酬の内訳は大きく以下の2つ。
【1】被保険者 ⇒ サービス提供事業者(被保険者の自己負担は1割~3割)
【2】市区町村 ⇒ サービス提供事業者(介護保険の負担は7割~9割)
介護保険の財源は、公費(50%)と保険料(50%)からなり、サービス提供事業者が市区町村へサービス費用を請求することで、2ヶ月後に介護報酬が発生します。
介護報酬の料金は一律ではなく、事業所の運営体制(サービス種類・利用者の状況、利用者の介護度)や、取得する加算の種類などで変わってきます。
介護事業所の収益は、この介護報酬が大部分を占めており、介護保険制度と合わせてしっかりと把握することが大切です。
適応できるサービス・対象者は?
介護保険サービスには、要介護認定を受けた人が利用できる【介護給付】と、要支援認定を受けた人が利用できる【予防給付】の2つがあります。
基本的に、要支援・要介護認定を受けた人は、上記2つの給付の対象者となります。介護認定を受けていない人で、緊急・その他やむを得ない理由があり、障がい福祉サービス等が必要と市区町村が判断した場合のみ、特例介護給付費・特例訓練等給付費という形でサービスを受けることができます。
事業所にどうやって売上が入るのか
介護事業所の売上は【介護報酬】によって決められるといっても過言ではありません。
介護報酬は、3年に1度の法改正で見直しが行われ、令和3年度の報酬改定ではプラス改定(介護報酬 0.7%増)となったことから、国として介護ニーズが増えていることが伺えます。
また、介護報酬は対象者の要介護度と、適用される介護サービスごとに決められた単位数(1単位:10円)に応じて介護事業所に支払われ、そこから運営費を差し引いた分が事業所の利益として計上されます。
例えば、介護の経営支援ソフトとして展開している【カイポケ】なら、職員の勤怠や給与振込、利用者の口座振替など、さまざまな機能で経営をサポートしてくれます。
具体的にどのようにしたら利益をだせるのか
企業の利益は、簡略化すると以下のように表すことができます。
[利益] = [売上] – [コスト]これを介護事業所で考えた場合、以下のように置き換えることができます。
[事業所の利益] = [売上(介護報酬)] – [コスト(主に人件費)]つまり、事業所の利益を伸ばすためには「利用者を増やす(売上を増やす)」か「人件費を抑える(コストを減らす)」ことが重要です。以下でもう少し具体に落とし込んでみましょう。
利用者を増やす(売上を増やす)
収益を上げる方法のひとつに、介護報酬を増やすことが挙げられます。介護報酬を増やすためには、高度な加算を取得したり、医療と連携して加算を取得するなどがありますが、設備やノウハウが整っていない中でそれらをいきなり始めるのは難しいですよね。

今回は、もっと簡単に介護報酬を増やす方法として、【介護事業所の利用者を増やす】方法をご紹介します。
介護事業所の利用者を増やすポイントとしては大きく2つ、【①介護事業所のサービス充実】と【②営業方法の検討】が考えられます。
まず、利用者を増やすためには、数ある事業所から「この介護事業所を利用したい」と利用者に思ってもらうことが重要です。利用者に選ばれる介護事業所を作るためには、自分たちの強みや、充実したサービスを提供することから考えてみましょう。
例えば「静穏な環境でゆっくりできる場所」「希望の利用者には洗濯物を無料で行う」「デイサービス独自のリハビリを取り入れる」など、最低限の費用対効果を考えながらも、自分たちが運営する介護事業所独自の強みを作ることが大事になります。
介護事業所のコンセプトや強みが生まれたら、【営業方法】についても検討する必要があります。
利用者は、介護サービスを選択する際に地域包括支援センターへの相談や、ケアマネを介して紹介される場合がほとんどです。新たな利用者を増やすためには、介護事業所の売り込み方を考える必要があります。
例えば、香川県の介護事業所では自身の介護事業所のセールスポイントを抑えた記事を載せた独自の新聞を作成し、配布する取り組みを行っています。それに加え、1か月の営業スケジュールを立て、計画的に営業を行った結果、利用者数は約500名、利用者の全体満足度も46%から85%まで向上が見られた事例もあります。
人件費を抑える(コストを減らす)
人件費を抑えるためには、まず【人件費率】について理解する必要があります。人件費率とは、売上に対してかかっている人件費がどの程度かを表す指標で、次のように計算します。
[人件費率] = ( [人件費] / [介護報酬] × 100 ) %建物を必要とする通所介護の場合で、人件費率は60%前後が適正と言われており、もし人件費率が60%を超えているようであれば、人件費の削減が必要です。
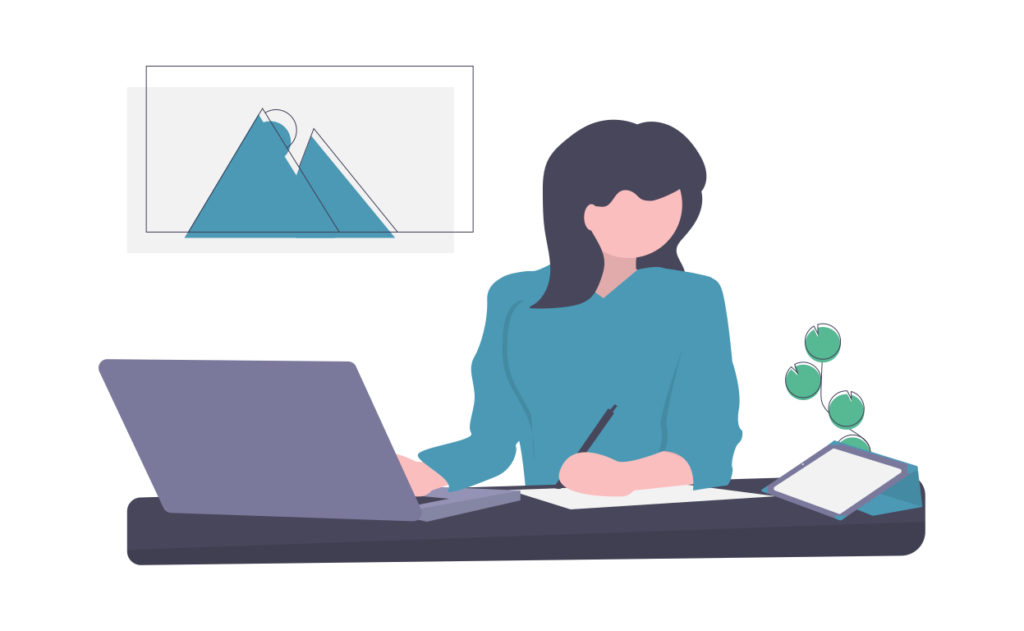
「人件費を減らす」というのは、なにも職員を解雇しろ・給与を安くしろ、というものではありません。まず目を向けるべきコストは【残業代】であり、つまりは職員の【残業時間を減らす】ことです。そして、介護現場における残業の大半が、介護記録の転記などによる事務作業が原因と言われています。
事務作業の効率化は現在、介護ソフトを用いて記録作業やデータ管理を行っていくことが主流となってきてます。ソフトによってはタブレットと連携し、訪問・移動の合間や、介護サービスを行った直後に記録・入力できるシステムもあり、導入した事業所からは「月間の事務時間が1/3になった」「残業時間がゼロになった」などの声もあります。
介護の経営支援ソフトとして展開している【カイポケ】なら、タブレットなどを活用して訪問先から記録作業ができたり、それによる転記作業もゼロにできてオススメです。
介護保険ビジネスの市場規模と将来性
現在、日本の要介護者は【666万人:令和1年】から【679万人:令和2年】の1年間で約10万人増加し、それに伴い2019年の介護保険の総費用は11.7兆円、65歳以上が支払う介護保険料も5,869円まで引き上げられています。
要介護者が増加するのに比例して介護事業所の数は増加しており、日本における介護の必要性は年々高まっていますが、2020年の介護事業所の収支はコロナウイルス蔓延の影響もあり、全てのサービス事業所において前年度の収支差比率がマイナスとなっています。介護事業所が増えている中、各介護事業所自体も収益増加に繋がる介護事業所経営を見直す必要があります。
今後の介護保険ビジネスの必要性
これからの日本において、少子高齢化の影響も受けて介護ビジネスの需要は更に増すことが見込まれていますが、介護事業所全体の収支自体はマイナスとなっています。
現在の介護ビジネスは介護保険制度を利用したものがベースとなっていますが、介護事業所の運営に関しては運営費用をうまく抑えることができず、運営に多くの費用がかかっている事業所も多くあります。今後、介護ビジネスを成長させていくためには、介護事業所に入る介護報酬を増やすだけでなく、各事業所で新規性の高い取り組みを行っていくことも一つの手かもしれません。
介護報酬改定とビジネスチャンス
混合介護の活用
近年、介護保険を利用したサービスの運営に加えて、介護保険外サービスを展開している事業所も増えてきています。介護保険外のサービスには理美容サービスや買い物代行、個別の同行などさまざまで、これらのサービスを併用することで、事業所の利益が増えるだけでなく、介護サービスとしての質も高めることができるでしょう。
特定処遇改善加算
特定処遇改善加算は、優れた介護職員に対して【全産業の平均年収である440万まで報酬を引き上げる】ための取り組みとして設けられました。介護職員のキャリアパスを考えるにあたり、賃金の向上は介護職員のモチベーションに繋がり、離職を防ぐことが期待されています。
また、介護職員のモチベーションを上げることは、介護事業所の収益アップに向けたアイディアや環境を新たに作り出す糸口になることも考えられます。
海外での介護事業
日本は世界でもトップクラスに少子高齢化が進んでいる国と言われていますが、海外の他の国での介護事情はどのようになっているのでしょうか。

介護・福祉が充実した国の一つとして、スウェーデンがあります。スウェーデンではコミューン(日本でいう市町村)が中心となり、介護サービスを提供しています。
スウェーデンは世界でも税率が高い国として有名で、これらの財源確保が十分にできていることから、全ての国民は無料で介護を受けることができます。
また、スウェーデンで行われている特徴的な取り組みの一つとしてホームレスパイトがあります。これは介護を行う人のために作られた制度で、介護者が少しでも休むことができるようにコミューンのスタッフを交代で在宅介護に派遣するシステムです。加えて「何でも屋」の位置づけもあり、要望があれば可能な範囲のサービスを提供します。
このような海外の介護に関する取り組みを、日本の介護保険内・保険外で行うことができるか選定して実践することで、介護事業所の収益を上げるヒントになるでしょう。
まとめ
ここまで、介護保険ビジネスの儲かる仕組みと将来性についてご紹介してきました。最後に、この記事の内容を3つのポイントにまとめましたので、振り返りなどにお役立てください。

- ポイント①:介護報酬の仕組みをしっかりと理解することが重要
- ポイント②:介護事業所の運営において削減すべき経費を見直すこと
- ポイント③:介護事業所の強みに合わせて、利益に繋がる介護サービスを伸ばす
請求業務はもちろん、タブレットによるICT化や、人材採用のサポート、利用者への口座振替、職員への給与振込…などなど、多くの機能を兼ね備えており、あらゆる介護事業所の経営をサポートしてくれます。